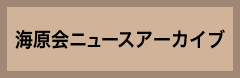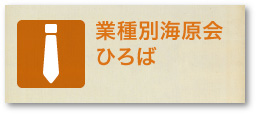クラブ・委員会ひろば
クラブ・委員会ひろば
<海城吹奏楽団第20回定期演奏会開かれる>(1)
第20回母校吹奏楽団定期演奏会が今年も去る5月6日、中野ゼロホールで開催された。
皐月の澄み切った空に、今や盛りのツツジの花が映えるなか、ホールへ急ぐ。
サポーターの若々しいお母様方の歓迎を受けるのは例年のとおり。
会場内は、女学生も混じり華やいだ雰囲気に一段と色を添え、かつての泥臭い男の集団であった往時との差異をいやが上にも感じざるを得ない。
客席に中には、植木前海原会長、立石海城学園後援会長の顔も見える。
今年3月退職された福島先生が、引き続き司会進行を担い、演奏曲目の紹介など相変わらずの名調子で観客を和ませる技は流石だ。
今年は、玄人好みの吹奏楽曲が多く、その中で「ザ・ブルース」の演奏は、まさに乗り乗り。
Chicagoで生まれたブルースが、洗練されてジャズの母胎となっただけに団員の演奏は吹奏楽から一歩出て、グレンミラー風のあかぬけた響きに変り、聞く耳に心地よい。
それに「One More Time」の掛け声と手拍子で観客との一体感を醸し出す手法に脱帽。
(続く)
文 安藤 浩(S34年卒)
画像 池内 宏(S33年卒) 石原長夫(S33年卒) 杉山紘千佳(S36年卒)
画像上:鑑賞に訪れたOB
画像中:鑑賞に訪れたやなぎ屋のおばちゃん
画像下:軽妙なトーク絶好調の福島先生
<海城吹奏楽団第20回定期演奏会開かれる>(2)
今年のもう一つの特徴は、「レトロ歌謡曲集」と銘打って「宮さん宮さん」、「おっぺけぺ」「ああ玉杯に花うけて」から「君恋し」「りんごの唄」など、明治、大正、昭和の懐かしのメロデーを見事に奏でて見せたくれた。
類似の試みとして、「わらべ歌メドレー」も好企画。
アンコール曲「フィエスタトロピカル」は、パーカッションの巧みなリズムさばきと、佐藤先生の時に荒々しく時に、たおやかなタクトに乗って、今にも踊りだしたくなるような南国の祭りの情景を思い起こさせる。
こうしたサンバやボサノバ調の陽気で華やかな曲目が、KWE(海城ウィンドアンサンブル)に一番合っているようだ。
最後に特筆すべきは、吹奏楽団OB会が、今春発足し、そのお披露目として、「風になりたい」を演奏してくれた事だった。さすが先輩の貫禄よろしく、実に軽快に、豪快に奏でてくれた。
パーカッションの派手派手アクションもさることながら、フルートの透き通るような音色、アルトサックスの甘い香りを漂わせる響きに酔いしれた。
次回からは合同演奏を是非企画してほしいものだ。また、これだけの実力をもつOB楽団だけに、出来たら海原会総会や、海城祭などでも、演奏を願えればと思う。
大変気分爽快な午後のひとときをどうもありがとうございました。
(完)
文 安藤 浩(S34年卒)
画像 池内 宏(S33年卒) 石原長夫(S33年卒) 杉山紘千佳(S36年卒)
画像上:現役演奏
画像中:現役演奏
画像下:OB会演奏
古賀理事長と徳光会長の座談(10)
会報「海原」37号で巻頭特集された古賀理事長と徳光会長の座談の全文を10回に分けて掲載いたします。こちらは第10回(最終回)です。
==============
徳光
父母会と海原会との結びつきはあった方がいいと思いますか?
古賀
あった方がいいですね。卒業生は海原会に全員入ることになりますが、保護者は希望される方だけでいいと思うんですよ。賛同されたかたに入ってもらうのがいいんじゃないかと思います。
徳光
なるほど。それは常任幹事会に諮ってみましょう。
ひとつの設問で色々な答えが返ってくるから楽しみです。錚々たる方がいますから良いアイデアが出るでしょう。
古賀
よろしくお願いします。
保護者の方には錚々たる人がいらっしゃる。びっくりする人がおあられますよ。
徳光
ところで那須校は今どのようになっていますか。那須校は教育の理想形でしたよね。あそこには戻れないですか。
古賀
あれは先行教育の最たるモノでしたが、震災と原発事故で避難ということになってしまいました。もうあの場所に帰ることはないでしょう。残念ながらしかたありません。廃炉まで40年という話でしたが、やっぱり順調にはいかない。それどころかもっとひどいモノができている。放射能が出る前に避難できたのが幸いでした。戻る選択肢はない。できない。
今のところ(多摩市)でやっていくでしょう。まずは今いる生徒を卒業させて、一時閉校にするつもりで対応してます。
徳光
残念ですね 人間教育という面では那須は素晴らしいなと思っていた。生徒の会話があるしね。
古賀
それこそ全寮制の仲間はそれこそ一生通じての友人です。
徳光
那須海城の空気と言いますか、海城学園として生徒たちに教え、教えられたことはあったと思います。那須での教育を本校に活かせたら良いですね。
古賀
生きているものも沢山ありますしこれからもあるんじゃないですか。
徳光
どうもありがとうございました。
(完)
古賀理事長と徳光会長の座談(9)
会報「海原」37号で巻頭特集された古賀理事長と徳光会長の座談の全文を10回に分けて掲載いたします。こちらは第9回です。
==============
古賀
生きた情報提供者が海城OBの中にはたくさんいます。
集中講座とか特別講師とやって頂かないとかそういうことをしないと生徒側の要求に応えられない。
徳光
実現性あるかなあ。ありますよね。
OBとしても学校との新たな結び目ができていきますね。
古賀
特任教授みたいにね。海城OBは各分野にいろんな方がいらっしゃいます。ただ、学園としては把握はできていません。分科会がたくさんできたら、まさに人材バンクですね。
徳光
海原会頼んだぞ、ということですね。蒼々たる人材のいる分科会に声をかけて、と、まさに海原会は事務局でしかるべき存在になっていくんでしょうね。
かわいい後輩ですよ、年が離れても。電車で学ランとあのバッジを見ると、あ、後輩だ、と思っちゃう。そういう気持ちがあるから協力できるんです。そのためには学校元気でいてもらはないといけませんね。
まずは海原会の方では人材の把握と整理ということですね。海原会として協力を促すという事をやってみたい
海原会としてもどういう人材がいるか把握しないと・・
古賀
それは絶対やって頂きたい。お金は学校が考えるから、それ以外をやってほしい。具体的に言うなら後輩を育てるということですね。
(続く)
古賀理事長と徳光会長の座談(8)
会報「海原」37号で巻頭特集された古賀理事長と徳光会長の座談の全文を10回に分けて掲載いたします。こちらは第8回です。
==============
■125周年にむけて学園が目指すのもの■
■OB会としての海原会の役割について■
徳光
話が違うんですが、あと数年で125周年ですが、何か考えていることはあるんですか。
古賀
100年までは10年ごとに式典を開いてきました。ここから先は25年ごとと決めたんです。125年、150年、そして200年。100周年のときにはパーティーの司会をしていただきましたね。でも、これからはそういう時代じゃない
125周年は校内の教育環境をよくすることを計画しています。
校舎を1つつくります。理科教育の殿堂を作るんです。ハードとして校舎を作ることは決めました。ソフトに関して、理科の人たちに話を聞いているところです。今までに無い、一時代先の理科は理科教育とどんなもんだろうと。キャンパス全体が理科的に考えていきます。例えば、自然エネルギーを使ったインフラの導入とか。理科をひとつのテーマとしてキャンパスを変えたいと思ってます。社会教育に加えて理科教育
徳光
若者の柔らかい頭脳ですからね。とてつもない発見とか何がでてくるかもしれませんね。
まさに次へ向けて踏み出した海城学園ですが、海原会としてお手伝いすることはありますか?
古賀
そういうときの人材なんですよ。海原会には人材をいただきたい。
これからの学校は、学校だけで何かをやろうとしたって限られたことしかできません。学校教育には期待が高まっていますが、学内だけじゃ対応できないんです。そうなってくると、いかに外と繋がるかが鍵になってきます。海外も含めいろんなところとつながっていろんな人材をいただいて、在学している生徒に最高の教育を提供する、それが私たちが求めていることです。できるかどうかが勝負じゃないかと思っています。海原会という人材の宝庫からご提供いただきたい。
徳光
今は情報社会であるからネットで調べればわかることは多いです。しかし、生きた情報は体験者から語られた方がずっと伝わるモノなのです。
古賀
若者はナイーブで真っ白だから伝わるんですよね。ネットじゃ取れない情報はあるんです。
(続く)
リニューアル以前の記事は旧 広場で見られます。